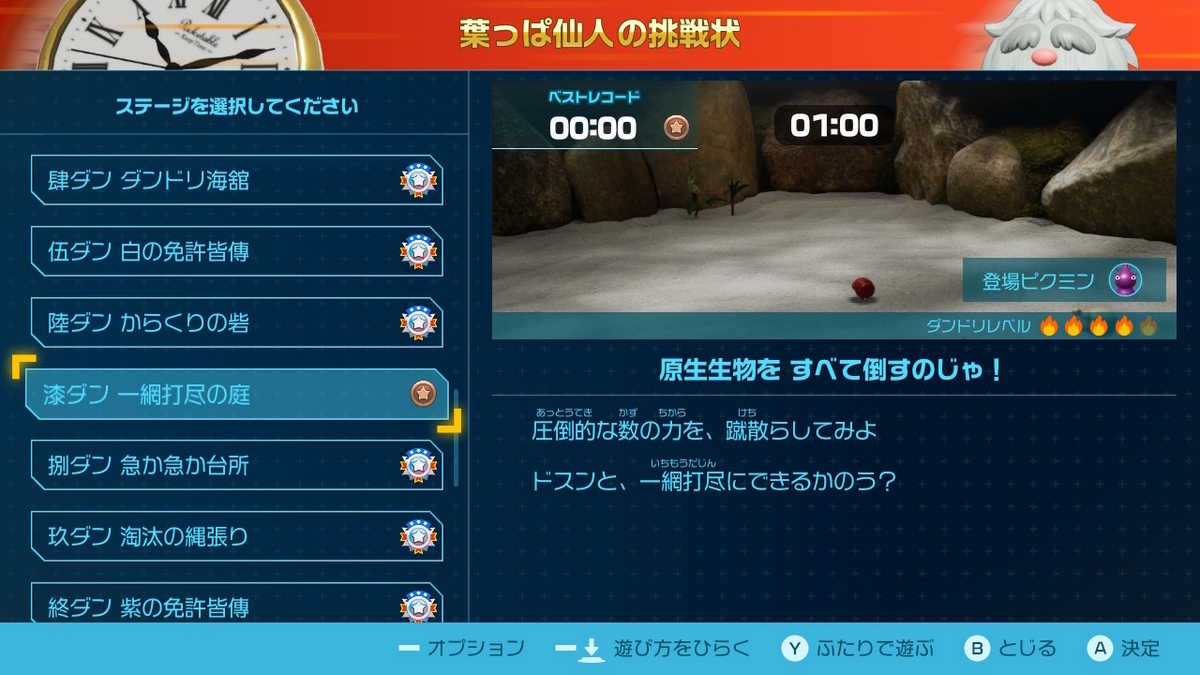ファイアーエムブレムは、味方の死亡をゼロに抑えつつ、味方より圧倒的に多い敵を殲滅するという、非常に高度なプレイングを求められる戦略ゲームです。
敵を殲滅する方法は、①自分から攻撃して敵を倒す、②敵に攻撃してもらって反撃で倒す、のいずれかです。①の方法にも強い戦法は存在し、例えば遠距離攻撃で敵を射程外から殴り続ける*1、強力なコマンド技で敵を確殺し続ける*2、などは非常に強力です。しかし、この方法では1ターンに1人1キルを稼げるのみであり、大量の敵には対処できません。
そこで、②の、敵に攻撃してもらって反撃火力で倒す、という戦法が重要になってきます。反撃で敵を一掃する戦法を、地雷戦法と呼びます。
地雷戦法は、一度完成してしまえば、後はそのユニットを置いておくだけで勝手に敵が消滅していくという、最強格の戦術です。その強さゆえに、開発サイドからの警戒度が高く、シリーズが進むごとに対策が強まっている戦法でもあります。そこで、本記事では、地雷戦法の概要と、シリーズでの変遷をまとめてみました。
なお、下記では、各作品を最高難易度でプレイすることを前提とします*3。
地雷戦法の概要
地雷戦法と一口に言っても、その実現方法は多種多様。まずは、地雷戦法にはどんなものがあるのか、具体例を見ていきましょう。
地雷を行うに当たって何より重要なのは防御方法です。1ターンに複数の敵から攻撃を受ける地雷戦法においては、まず複数回の攻撃を受けても生存できるユニットが居なければ話になりません。
加えて、反撃で敵を確殺できる火力をどう出すかも重要です。敵を仕留め損ねていては、次ターンに再度攻撃を受け、一気にピンチに陥るでしょう。
以上の防御方法・反撃方法の実現手段はいくつかあり、その分類を下記で紹介します。
防御方法の分類
守備地雷

敵の攻撃を耐え抜く最も基本的な方法は、守備力を高めて敵の攻撃を弾くことです。例えば、「蒼炎の軌跡」や「新・暗黒竜と光の剣」といった作品では、自軍壁役の守備力上限が30に対し、終盤の敵の物理攻撃力は精々25〜35程度。つまり、ジェネラルなど硬い兵種を使っておけば、敵の攻撃を最大数ダメージ、良ければノーダメージに抑制できてしまいます。
しかし、このような状況を毎作容認する制作サイドではありません。近年は、攻撃60〜80にもなる超火力の斧兵や、守備デバフ能力を持つ盗賊、壁役の不得意とする魔法砲台など、対策ユニットがマップに配置されること多数。こういった攻撃を受ければ、壁役の堅固な装甲も貫かれ、守備地雷戦法は簡単に崩されてしまいます。
回避地雷

超火力、デバフ、遠距離魔法、といった多様な攻め筋に対抗するにはどうすれば良いのでしょうか。一つの回答は、「危険な攻撃には当たらないこと」です。回避率を高めて、敵の命中をゼロにすれば、どんな攻撃も怖くありません。回避率が速さ×2という高い水準で算出される「烈火の剣」や、地形効果で最大+60%の回避上昇が受けられる「外伝」などにおいて特に有効な戦法です。
しかし、制作サイドからの対策も当然バッチリ。近年では、命中率を底上げするスキルを持った敵兵や、地形効果を無視する攻撃が増え、回避地雷も崩されやすい環境になってきています。
回復地雷

敵からの攻撃を受けきれず、避けることもできないと、被ダメージは必至。しかし、そのダメージを即座に回復できるなら、生き残って反撃が可能となります。HP吸収魔法が豊富に入手できる「覚醒」や、回復奥義が強力な「暁の女神」では、回復地雷戦法が有用です。
しかし、この戦法に対する開発サイドからの規制は厳格。回復技の性能や使用回数には厳しい制限が掛かっていることが多く、容易に成立する戦法ではありません。
先制地雷

敵の攻撃を受け切れず、避け切れず、回復もし切れない、というのが近年のFEに多い傾向です。残された最終手段は、そもそも攻撃される前に倒してしまうこと。FEのスキルの中には、敵から攻撃された場合も、自分が先に攻撃できる、というものが存在。先制スキルの充実している「ヒーローズ」や「風花雪月」などでは、先手を取って全ての敵を倒してしまう先制地雷戦法が強力です。
こういった複数の戦法をうまく組み合わせて使っていくことが、地雷戦法のキモになります。
反撃方法の分類
手槍地雷 / 手斧地雷 / 魔法地雷

上では、敵の猛攻をいかに耐え抜くか、の方法を紹介しました。攻撃を耐えた後は、敵を反撃で屠らなくてはなりません。
反撃時に重要なのは、武器の射程です。地雷戦法では、どうしても直接攻撃・間接攻撃の両方の武器の入り混じった敵軍から袋叩きにされます。両者に反撃できるよう、直間両用の武器を装備することが求められます。
反撃手段として最もメジャーな武器は、手斧・手槍・魔法の3種類でしょう。手斧使いの層が厚い「トラキア776」や、光魔法を魔物特効とできる「聖魔の光石」などでは、手斧地雷や魔法地雷が非常に優秀です。
但し、古来から存在するこの戦術には、制作サイドからのメスが何度も入っています。近年は手槍・手斧の反撃火力がガンガン落とされ、現代の戦いには付いて来れない戦法になりつつあります。
必殺地雷 / 奥義地雷

反撃火力を補う方法として挙げられるのが、反撃時に必殺や奥義を発動できるようにする方法です。武器の必殺率を盛る手段が豊富な「エンゲージ」や、奥義加速手段が手厚い「ヒーローズ」で有効な、現代風の戦法です。
採点基準
このような地雷戦法の、各シリーズ作品での強さの変遷を、下記では紹介していきます。作品ごとに、地雷戦法の強さを評価していきます。地雷要因に求められる性能は、大きく分けて下記の5つでしょう。
- 敵の猛攻に毎ターン晒されても地雷要員が安定して生存でき、継戦力が高い
- 反撃火力が高く、敵を1戦闘で撃破しやすい
- 地雷要員の能力上げやスキル習得といった育成が低コストで完了する
- 序盤から終盤まで、地雷戦法の活躍期間が長い
- 地雷戦法に、他の戦法と比較した優位性がある*4
以上の継戦力・反撃火力・低コスト・長期間・優位性の5つの項目を1つ満たすごとに1点とし、5点満点で採点を行いました。0, 1, 2, 3, 4, 5点をそれぞれE, D, C, B, A, Sと表記します。また、作品ごとに、どの項目が満たされているかも記載します。
地雷戦術の歴史と評価
暗黒竜と光の剣&紋章の謎:A

まだ制作サイドから地雷対策がほとんど成されていなかった初代FE。基本的な直間両用武器を用いた手槍地雷、手斧地雷、魔法地雷はいずれも便利でした。
その中でも特に使いやすかったのは、重量0~2と破格の軽さを誇っていた初級魔道書です。例えば、ブリザーであれば、威力5で重さがたったの2。速さの高い司祭に装備させて、森などの回避地形に立たせれば、お手軽に魔法地雷が完成します。
司祭の中で最も地雷向きのユニットはマリクでしょう。魔力・速さともに伸びが悪くなく、回避率と反撃火力ともに優秀。その上、魔法系らしからぬ高いHP成長率を誇るため、回避し損ねて被弾しても、しぶとく生存できます。
本作でエースユニットと言えるオグマやナバールは、いずれも近接攻撃の専門家。直間両方の増援が大量に湧くマップでは、敵の殲滅に手間取ります。そういったマップで、敵を一掃できる魔法地雷は非常に有難い存在でした。
但し本作品では、FE黎明期であったがゆえに、回避を盛る装備やスキルは未登場。回避地雷戦法をしようにも、基本的には敵の命中をゼロにはできず、事故の危険性が付きまといました。守備無視のブレスやドゥラームを被弾して一気にピンチに陥ることもあり、継戦力は低めでした。
外伝:B

前作とはシステムが打って変わり、一般武器の射程が強化された本作。射程1~3のサンダーや、射程1~5の鉄の弓といった、反則級の攻撃が自軍を襲います。射程1-2の手槍やファイアーでは反撃ができず、一方的に殴られるだけに。地雷戦法は一気に弱体化しました。
そんな本作において、唯一地雷向きと言える装備品が「聖なる弓」です。この武器は、威力が5と高めなのに重さが0という破格の性能を有します。射程も1~5であり、一般武器には必ず反撃可能。毎ターンHP5回復というリジェネ効果まで有するため、多少の被ダメも気になりません。
この武器を最も使いこなせるのは、力の伸びが優秀で反撃火力を確保しやすいアルムでしょう。速さもよく伸びるため、回避率+40%という稀代の高水準な地形効果が受けられる森や林に置いておけば、回避地雷として活躍してくれます。
但し、聖なる弓が入手できるのはアルム編のみで、入手タイミングも終盤。従って、この地雷戦法が使えるのはごく短期間です。総合して、地雷が特筆して強いわけではない作品、と言えるでしょう。
聖戦の系譜
未プレイのため不明。神器の性能が凄い作品らしく、地雷戦法も強そうな気がします。
トラキア776:A

紋章の謎や外伝と比べてシステムが練り込まれ、個性的なスキルや体格パラメータが導入された本作。「体格」は、その数値ぶん武器重量を軽減できるというパラメータであり、今まで重かった手槍や手斧の使い勝手が格段に向上しました。
また、新登場したスキルの中でも特に強力なのが、反撃時に必ず必殺が出るという驚異のスキル「怒り」です。これを持つオーシンやサラは、手斧やファイアーといった直間両用武器を装備して立っているだけで、勝手に反撃で敵を殲滅してくれる破壊神と化します。
加えて本作には、追撃時に必殺率が数倍にブーストする「追撃必殺係数」システムが存在。カリオンやリノアンといった係数の大きいユニットなら、反撃時に追撃を取れさえすれば、高確率で必殺を出して敵を粉砕してくれます。反撃火力の出しやすい本作において、地雷戦法の使い勝手は上々でした。
一方、本作には、自分から攻撃した際に敵を捕らえるコマンドが使用できるという、「捕縛」システムが存在。捕縛した敵の装備品を売却する金策を行わないとすぐに軍資金が枯渇する、というのが本作の難点です。地雷戦法は確かに強いのですが、反撃では敵を捕縛できないため、頼りすぎると財政難まっしぐら。取り扱い注意の戦法と言えます。
封印の剣:A

前作までのFEでは、プロデューサーである加賀氏により、長射程一般武器や捕縛システムなど、地雷戦法を相対的に不利にするシステムを導入する調整が行われてきました。しかし、同氏が退社した本作からは、そのような調整は終了。地雷戦法が本格的に強くなり始めます。
本作のシステムで特徴的なのは、敵軍出身者のステータスが数レべルぶん底上げされる「ハードブースト」です。これにより、5~10レベル分もステータスがブーストした優秀な前衛ユニットが多数輩出されました。力・速さ・守備のいずれも高水準である彼らは、反撃火力・回避率・耐久力の全てに優れるため、地雷戦法をさせると一級です。特に、戦場を自由に飛び回って手槍地雷を展開できるミレディ、バーサーカーの兵種補正で必殺地雷を仕掛けるゴンザレス、自軍最高レベルの速さで回避地雷を行えるルトガーなどは、まさに一騎当千の活躍をしてくれます。
一方で、今作の地雷のメインウエポンとなる手槍や手斧は、基本的に威力が控え目。必殺が出ない限りは、殲滅速度は遅めでした。
烈火の剣:S

細かい調整を排したシンプルなゲームシステムで、初心者への間口を広げた前作。それに対し本作では、前作までを経験した熟練プレイヤーを唸らせる、高難易度ルートが搭載されました。最高難易度モードでは、最小5人程度という異常に狭い出撃枠と、敵100体湧き級の圧倒的物量、厳しいターン制限がプレイヤーを襲います。少人数の味方で大量の敵を短時間で処理するには、地雷戦法で敵を一掃するプレイングが必須となってきます。
幸いにも、今作は防御力や回避率に優れた優秀なユニットの宝庫です。ヘクトルとオズインは力・守備が非常に高い重装兵であり、敵の攻撃を弾きつつ手斧で反撃火力を出せます。プリシラとパントは速さ・幸運が高く育ちやすい魔法職であり、敵の攻撃を回避しながら軽い魔法で反撃を狙いやすいです。
こういったユニットを駆使して、受け中心の戦闘を展開しないと勝てないのが本作。地雷の強さ評価は明らかに満点です。
聖魔の光石:S

前作に引き続き、遠慮のない物量の敵が湧く本作。終盤は、100体近くの魔物が自軍に襲い掛かるマップが連続します。そんな厄介なマップで必須なのが、反撃で大量の敵を処理する地雷戦法です。
今作の魔物は、大部分が低速・低守備なステータスを持ちます。従って、手槍・手斧・魔法など軽い直間両用武器で2回攻撃をすれば、撃破は容易。アメリアやジストといったタフな斧兵による手斧地雷、ターナやエフラムといった攻撃的な槍兵による手槍地雷は強力でした。
そして、彼らを凌ぐ本作MVPの地雷用ウエポンと言えば、光魔法でしょう。軽くて耐久値が高い上、スキル「魔物特効」を所持する司祭が使えば威力3倍となります。司祭の中でも特に地雷向きのユニットは、ナターシャでしょう。速さ・幸運ともに優秀で回避率が高く、森の上に置いておけば、魔物相手に無双してくれます。
GBA3作では、敵味方共に回避率が高く設定され、回避地雷が特に強い時代でした。そんな流れに歯止めを掛けるべく、次回作からは製作陣により地雷戦法へのメスが入り始めます。
蒼炎の軌跡:A

「避けて殴って終わり!」の戦闘環境を変えるべく、敵味方の火力に大幅デフレ調整が掛けられた本作。特に武器威力の低下が凄まじく、例えばエルファイアーは威力10→5、アーマーキラーの特効威力は18→12、などと激しいナーフが入ります。前作までのように、魔法職や斧兵を置いておいて、回避地雷で敵を一掃、などという戦法は通用しなくなりました。
一方で、本作の仕様で強化されたのが、パワータイプのタンク職です。魔法や特攻武器が弱体化したことで、ジェネラルやドラゴンマスター等のクラスは、怖いものなしで戦場を闊歩できるように。減った反撃火力は、本作で導入された「奥義」や新スキルで補い、守備地雷を展開できるようになりました。
地雷ユニットの代表格が、主人公アイクです。射程1-2の優秀な専用剣ラグネルを持ち、武器補正を加えた守備上限値は29。終盤でも敵の攻撃力が30~35程度に留まる本作では、非常に場持ちします。その上、奥義「天空*5」により火力と回復力も十分。適当に育てても優秀なステータスになるため、育成も簡単です。
また、ジェネラルであるガトリーとチャップを使った地雷も強力。本作のジェネラルは、「騎士の護り」を付ければ守備32を実現でき、まさに不沈要塞です。更に、スキル「勇将*6」「怒り*7」を習得させれば、HP半分時に速さ36、必殺50%となります。これにより、敵ソードマスターにすら追撃を取り、75%の確率で必殺を出して屠ってくれるという、化け物じみた活躍を見せてくれます。
その他、ドラゴンマスターのジルやパラディンのケビンによる手斧地雷も優秀。依然として地雷の強さが損なわれていない作品と言えます。
暁の女神:A

守備方面にバランスを傾けすぎた前作の反動か、武器威力や特攻倍率がGBA時代相当に戻された今作。前作で鉄壁を誇った重装兵や騎馬兵は、守備面が不安定となり、鳴りを潜めます。
その一方で、ドラゴンナイト系は、今作で弓と風魔法が特効ではなくなるという強化を受け、一気に空飛ぶ要塞へと躍進します。最上級職「神竜騎士」になれば、パラメータは力38・速さ32・守備38というとんでもない値に。ショートアクスやトマホークといった高威力斧を使った地雷戦法で大活躍してくれます。特に今作では、限られたターン内に貴重なアイテムを回収する必要のある防衛マップが多く、短時間での殲滅戦に欠かせない戦力です。
また、前作に引き続き、アイクによるラグネル地雷も優秀。今作では使用武器に斧が追加され、ラグネル未入手の中盤から手斧地雷ができるように。天空による回復力も健在です。
ただ、魔法威力が上昇した今作では、地雷要員の生存力が不安定に。特に、雷魔法による竜特効や必殺により、ハールやアイクといったエースを落とされる事故も多数発生。継戦力には全幅の信頼が置けません。
新・暗黒竜と光の剣:S

プレイの自由度の少なさが指摘された前作の影響を受けてか、兵種変更システムの導入や武器錬成システムの強化など、遊びの幅が広がった本作。敵側もその恩恵に預かり、終盤では錬成勇者武器が敵の標準装備に。威力30ほどにもなる2回攻撃が自軍に降り注ぎ、賢者など柔らかいユニットは一瞬で蒸発します。
そんな火力インフレに対抗できる壁役として重宝されたのが、驚異の個人成長率445%を誇るウルフとザガロです。彼らがジェネラルに兵種変更すれば、圧倒的成長率で一瞬でパラメータがカンストし、守備は30に到達。敵の勇者武器を全て弾き、反撃の手槍で敵に大打撃を与える守護神へと化します。
過去作の地雷要員と異なり、ウルフ・ザガロは加入時期も優秀。第5章という最序盤から加入してくれ、次章から即座にジェネラルとして手槍地雷で戦ってくれます。敵軍戦力・自軍戦力の両方を鑑み、地雷戦法がシリーズ随一の強さを見せる作品と言えるでしょう。
新・紋章の謎:C

「取りあえずジェネラルで壁」の戦闘環境を崩すべく、敵の火力が更にインフレした本作。威力+4・命中+20という超ブルジョワ錬成*8が施された錬成銀武器が敵モブ兵に配布され、攻撃力45付近の超火力が自軍に降り注ぎます。HP60・守備30のジェネラルでは、追撃込みで2戦闘で撃破されてしまい、まともな守備地雷戦法が成立しません。
では、回避地雷ならどうなのか、というと、こちらも厳しい状況。Wii時代までは「速さ×2+幸運」で計算されていた回避率が、DSからは「速さ+幸運÷2」と大幅引き下げさを喰らっています。その上、武器レベルAによる命中率ボーナスの導入、敵武器の命中アップ錬成、ルナティックでの敵命中+10%補正、といった要素によりほとんど回避が行えない状態に。
かろうじて地雷戦法が有効なのは、まだ敵火力が伸びる前の序盤でしょう。マイユニットを速攻育成してジェネラルにし、難関マップの続く4章~7章を手槍地雷で攻略する、といった戦法は有用性があります。
公式からの規制が厳しく、ほとんど地雷に頼れない作品です。
覚醒:S

綿密に練られた前作までのゲームバランスが、新規導入されたダブルや無限育成といった革新的システムによって木端微塵に破壊された本作。公式からの地雷対策も崩壊し、エースが無双するだけの世紀末環境が展開されます。
インフレした敵火力は前作から健在なのですが、それにより受けたダメージを回復する手段が本作では充実。特に、勇者が取得できるスキル「太陽*9」を使えば、敵に攻撃されても即座に回復するゾンビ戦法が可能となります。太陽の効果を引き出すには反撃火力の確保が必要ですが、威力10のトマホークや威力18のスワンチカといった高火力投げ斧を使えばOK。これらの武器は耐久力の低い貴重品ですが、同じく勇者が昇格前に習得できるスキル「武器節約*10」を使い、バフで幸運を50以上にすれば、耐久力消費ゼロで攻撃できるように。ドニ・セレナ・アズールなど優秀な傭兵の存在もあり、太陽地雷戦法は一世を風靡します。
また本作では、与ダメージの半分を回復する闇魔法「リザイア」が店で無限に購入可能。これをソーサラーに装備させたリザイア地雷戦法も強力です。HP吸収が確定で発動する上、ソーサラーの習得スキル「復讐*11」により被弾後は回復力が上がるため、安定性が高いのが嬉しい所。
回復地雷の活躍により、シリーズ歴代で最も地雷戦法の強い作品と言えます。そして現状、FEの歴史上、地雷の強かった最後の作品でもあります。
if(暗夜王国):E

世紀末環境と化した「覚醒」の反省を受け、地雷による安易な勝利は絶対許さない、という鉄の意志で緻密な調整の施された「暗夜王国」。回復地雷に有用だったトマホークやリザイアには、「追撃不可」というナーフが入り、回復のための手数が出せなくなりました。加えて、封じ系スキルや手裏剣によるデバフシステムが導入され、地雷などしようものなら、そのキャラのステータスがズタボロに弱体化されることに。蛇毒や四牙といった割合ダメージを与えるスキルも登場し、回復が追い付かなくなります。その上、一撃系スキル*12や強者系武器*13など、攻め時に強力な効果を発揮する要素も新登場し、受け戦法が相対的に弱体化。
本作で唯一地雷戦法が使用可能な状況と言えば、群れて出てくることが多い魔法系を、スキル「魔殺し*14」装備のユニットで相手取る時でしょう。例えば、魔殺し習得が早く爆炎手裏剣で火力も出せるフェリシアや、魔殺しを遺伝で習得できる子世代ユニットなら、この戦法が可能です。とは言え、敵に物理系兵種や妨害杖持ちが混じると、魔殺し手裏剣地雷も簡単に崩壊し得ます。
総合して、シリーズ歴代で地雷戦法が最弱の作品と言えます。本作で強化された地雷対策は、次回作以降も続いていくことになります。
エコーズ:C

元から地雷戦法の強くなかった「外伝」が、受けより攻めを強くする「if」の思想を継いでリメイクされた結果、更に地雷が弱くなった本作。
リメイク元と同様、射程1-3の魔法や射程1-5の弓が多く登場し、射程1-2の手槍やファイアーでは地雷が成立しません。原作では強かった「アルム×聖なる弓」の地雷も、アルムの弓射程が1-3にナーフされて弱体化。聖なる弓自体も、威力が5→3、重さが0→2にと劣化し、実用圏外に。戦技システムの導入により攻め時の火力が重視されるようになり、反撃中心の戦法は下火となりました。
あえて地雷の使える場面を挙げるなら、ビグルやガーゴイル等の自由に行動させたくない近接魔物を、魔戦士など強力な近接兵種で迎撃する際でしょう。魔戦士を使う場合、魔物の殲滅力に優れる「聖なる剣」、高必殺率でバクチを仕掛けられる「勇者の剣」、HP吸収効果で粘り強く戦える「暗黒の剣」など、地雷向きの装備も豊富。武器消費無しで気軽に使えるワープとレスキューで、地雷要員の転送と回収もスムーズに行えます。
風花雪月:C

開発会社がコーエーテクモゲームズに変更になり、前作までと比べゲームバランスが緩まった本作。地雷戦法が綿密に対策されるどころか、むしろ地雷をアシストするスキルが多数登場しています。
特に、飛行系兵種のスキル「回避+10」「警戒姿勢+*15」を利用した回避地雷戦法は強力です。反撃火力を盛るスキルも揃っており、「怒りの陣*16」「切り返し*17」などは非常に有用。エコーズに引き続きモブ敵兵の射程1-3攻撃が厄介ですが、自軍も「サンダーソード+」など射程1-3で反撃できる武器が使用可能です。
では、こういった地雷戦法を積極的に採用したくなるかというと、そうでもありません。本作では、過去作のように敵が100体レベルで湧くステージが少なく、地雷で敵を掃討する必要に迫られません。また、「ハンターボレー」や「テュルソスの杖」による長射程攻撃で敵を一方的に嬲る戦法が強く、わざわざ敵を接近させて地雷に持ち込むまでもありません。その上、地雷戦法用のスキルを回収するために転職を繰り返す育成コストも重く、趣味レベルの戦法と言えます。
結論として、地雷戦法は実現可能なものの、地雷をするまでもない作品、と言えます。
エンゲージ:D

開発元がインテリジェントシステムズに戻り、地雷によるお手軽クリアは絶対阻止、という鋼の意志が復活した本作。ifで施された、武器ナーフ・デバフ・割合ダメージ・受け弱体化という地雷対策システム四天王は健在。特に、戦闘開始時に最大HPの10%を削るシステム「チェインアタック」により、守備地雷も回避地雷も成立しないのが辛い所。
本作でギリギリまともに運用可能と言えるのは、待ち伏せ+必殺武器による先制地雷でしょう。武器刻印「選択の紋章*18」とスキル「怒り*19」を合わせて必殺率を増し、スキル「待ち伏せ++*20」で攻撃される前に敵を撃破する、という戦法です。パネトネなど、高火力高必殺率のユニットが使えば非常に強力。但し、反撃を外す、必殺の不発、必殺を耐えられる、といった要因で敵を討ち漏らすと、普通に殴られてロスト必至。あまりに不安定な戦法です。
3~4ターン味方が強化される「エンゲージ」システムを利用した地雷戦法も考えられます。例えば、「踏ん張り+++*21」で攻撃を耐えて、エンゲージ武器「リザイア」で回復し、踏ん張りを再発動可能にする戦法。また、エンゲージスキル「絆盾」で守られた味方が、エンゲージ武器「ジークリンデ」の超火力で敵を倒す戦法。…といったように、エンゲージ時の強力な能力を絡めれば色々な悪さが可能です。しかし、大量の敵に囲まれたままエンゲージが切れると、一転して生命の危機に。継戦力には大いに問題ありです。
ヒーローズ:B

シリーズ本編と並行して開発が進められている「ヒーローズ」。攻撃が必ず命中するという特殊な戦闘システムで、命中率をゼロに落としたシリーズ恒例の回避地雷は通用しません。また、定期的に行われる新英雄召喚で、壁役の守備力を絶妙に上回るアタッカーが追加されるため、守備地雷も非現実的。そんな中で、受け時に自分が先に攻撃できる待ち伏せ系スキルを用いた先制地雷は、例外的に根強い強さを誇ります。
先制ユニットとして特に強力なのが、任意の1ターンに限って無条件で先制攻撃が可能となる、クリスマスオルティナです。専用武器「ラグネル&エタルド」は、1-2射程に反撃できる上、勇者効果で2連撃が可能。錬成で奥義カウント加速効果も付くため、2連撃の片方では奥義「双刃*22」が発動し、破壊力は抜群。お供に火力サポート要員を付ければ、ほとんどの敵を1戦闘で粉砕してくれます。先制できるのは1ターンの間だけですが、アビサルならその間に敵を全滅させてくれるため、問題になりません。
但し、オルティナのような強力な先制地雷要員や、優秀な火力サポート要員を揃えようと思うと、期間限定ガチャで頑張る必要があり、パーティ構築コストは高め。また、他プレイヤーが相手となる飛空城や英雄決闘では地雷戦法は簡単には決まらず、活躍の幅は限定的です。
まとめ
以上より、作品ごとの地雷戦法の強さの変遷は、次のようにまとめられるでしょう。
- 暗黒竜〜トラキア :原作者により地雷戦法が多少規制されていた
- 封印〜新暗黒竜:規制のタガが外れ、地雷戦法が猛威を振るう
- 新紋章〜エコーズ:規制が再度強化され、地雷戦法は冬の時代に
- 風花雪月〜エンゲージ :豊富なスキルを活用し、限定的な状況下で地雷戦法が可能に
戦略シミュレーションゲームとしては、綿密に練られたマップが、地雷戦法により手軽に突破されるようでは、遊び応えに欠けます。その対策として、制作サイドは、地雷戦法を規制するバランス調整を行なってきました。しかし、新紋章やifのように規制が強すぎると、プレイ感も窮屈に。そこで、近年の作品では規制がやや緩和され、地雷のパーツとして利用可能なスキルが抜け道的に残されています。これらを駆使することで、限定的な状況下では地雷が可能、という調整に落ち着きつつあります。
次回作以降は、どんな調整が施され、その結果どんな地雷戦法が生まれるのか、期待が高まります。
*2:エコーズのハンターボレー、風花雪月の連撃など
*3:マニアック、ルナティックなど。裏モードであるルナティック+や、課金要素であるDLCは対象外とします
*4:例えば、いくら地雷戦法が強い作品でも、遠距離攻撃で敵を事前に一掃する戦法の方が強い場合、地雷戦法の採用価値は薄い
*5:与ダメ分HPを吸収する攻撃と、敵の守備を半分で計算する攻撃の2連続攻撃を、技%で繰り出す
*6:HPが50%以下の時、力・技・速さ×1.5
*7:HPが50%以下の時、必殺+50%
*8:自軍が行うと1本15000G以上必要
*9:技%で、敵へのダメージの半分のHPを回復する
*10:幸運×2%で、武器耐久力が減らない
*11:技%で、HP減少分が与ダメに上乗せされる
*12:自分から攻撃した際に能力アップ
*13:自分から攻撃した際に2回攻撃
*14:魔道書装備の敵と戦闘時、命中・回避+50
*15:何もせず待機時、1ターンの間、回避+30
*16:騎士団の戦力が1/3以下の時、必殺+50
*17:HP50%以上で敵から攻撃された時、敵は追撃不可、自分は絶対追撃
*18:必殺+40の効果を武器に付与
*19:HP減少値が必殺率に上乗せ、最大+30
*20:HP75%以下で敵から攻撃された時、先制攻撃
*21:HP2以上で敵から攻撃された時、HPが1残る
*22:魔防の40%をダメージに加算